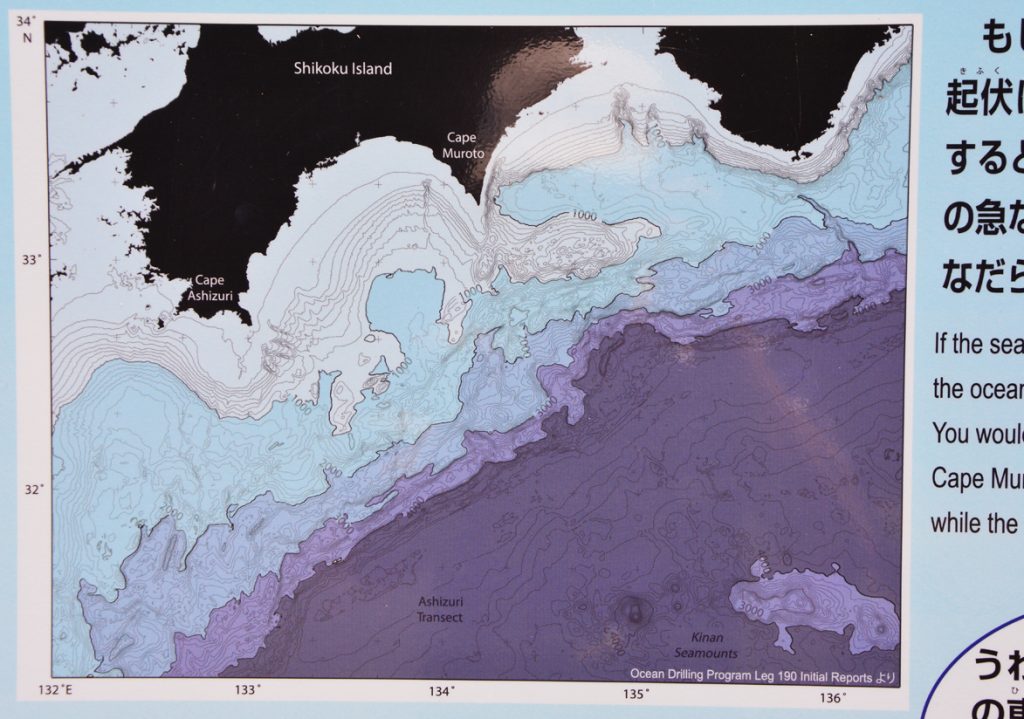1.棚田の地域
高知県の北部、徳島との県境に近い吉野川南岸に帯状に棚田地帯が伸びています.八畝(ようね)、怒田(ぬた)はその中にあります.

見た人が「マチュピチュだね!」と言いましたが、山の頂近くから谷底まで棚田が並び、家々が点在しています.

各家々が近くに見えていても、この斜面のどこをどう上るのかは難しく、そのため住居と道路を示す地図が沿道にあります.ただメインの道路は何となく一本道で、迷うことはありません.
2.棚田を見る

春、田植えが済んだ水田では蛙の声が盛んですが、投影面積の割りにひと区画の田は狭く、その間にある土手の傾斜が緩いことに気付きます.

周囲の山が見渡せる高所でも、水田には豊かに水が湛えられています.しかし溜池や用水路があるわけではありません.緩やかな傾斜と豊富な水、これがこの地域の特徴です.
地質学者によれば、この一帯は御荷鉾(みかぶ)帯と呼ばれる地質であり、その底部では、緑色岩が水による変成を受けて粘土化し、水を通さない厚い層をつくっているとのことです.その上に風化した層、長年に渡って崩壊した層が乗り、大量の水を過飽和なまで含んでいます.いわば洗面器に水を湛えた状態なのです.
3.地すべり対策
傾斜が緩く水が豊富、耕作には良いのですが、もともと地すべりが重なって生まれた地形なのであり、地すべりはついて回ります.

そのため長期に渡る国の直轄事業で地すべり対策工事が進められてきました.完了に近づいていますが、まだ進行中のところもあります.

河道を広げ護岸を行って水流を確保すると共に、ところどころの斜面に新しく排水路を設けています.

井戸を設けて斜面の水を集め放水します.近づくと水音が聞こえます.地下に多数の排水管を設置することも行われています.

斜面のところどころにGPS受信機を設置し、地盤の位置変化をモニターしています.
4.棚田の秋
地すべり工事はありますが、刈入れを終わった秋の棚田はのどかです.銀杏が金色に光ります.



地域には民宿があり、レーベンもその一つで、牧場があることからチーズづくり体験をしたことがあります.
5.山を巡る

八畝からの山腹を林道が西に向かって長く伸びています.分岐には人家もなく山に迷い込んでしまわないか不安になりますが、森と斜面を進んでいるとその内に土讃線の大杉駅に達します.

西には石鎚に連なる山並みが重なっています.朝霧が濃いということです.次第に冷え込んでくるのでしょう.
(初版:2020年12月4日) (改訂版:2022年4月1日)
2022年4月2日 改訂版